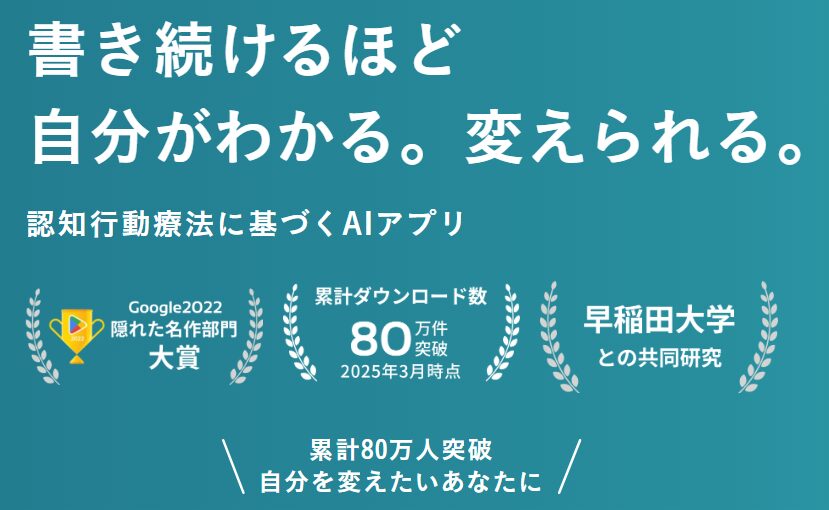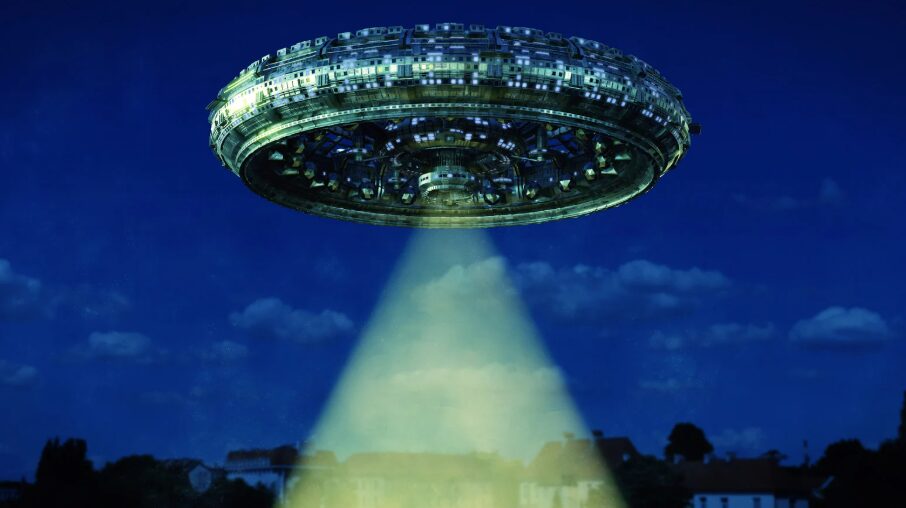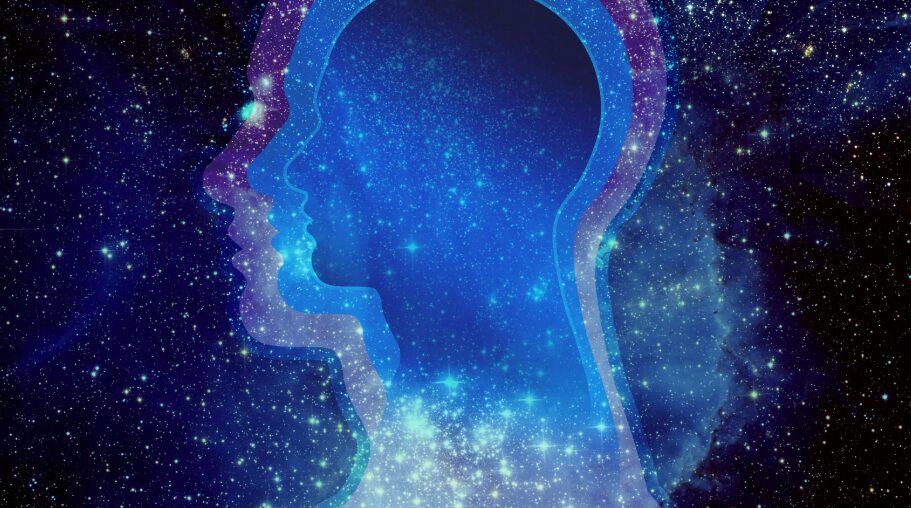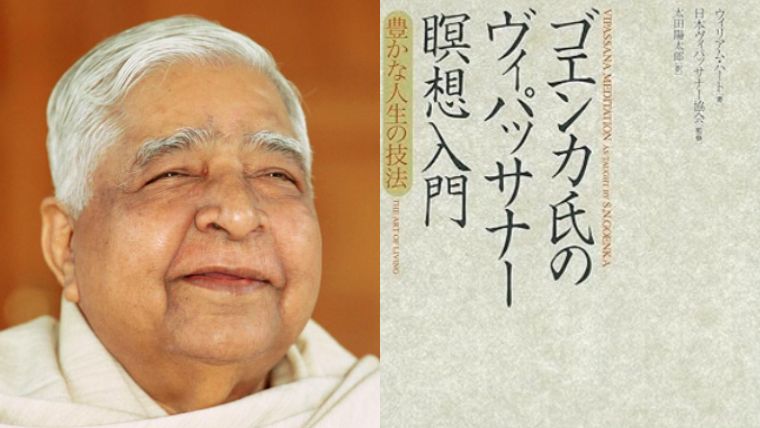瞑想の姿勢の種類はなんでもいい?最適な方法をわかりやすく紹介!

「瞑想はあぐらで座らないといけないの?」と思ったことはありませんか?実は瞑想にはさまざまな姿勢があり、無理に決まった形をとる必要はありません。
あぐらをかく「基本的な座法」は確かに効果的ですが、それだけが正解ではないのです。椅子に座る、横になって行う、さらには寝たまま行う方法など、姿勢は柔軟に選べます。
特に「姿勢がツラい」と感じる方にとっては、体に無理のない形で行うことこそが集中力を高めるカギになります。
また、瞑想の時間帯や目的によって最適な姿勢が異なることもあり、背もたれの使い方ひとつで猫背になってしまうこともあります。
この記事では、瞑想と睡眠の違いや、手の組み方・足の組み方の工夫まで、幅広く具体的に紹介していきます。あなたにとって最も心地よい姿勢を見つけるヒントになるはずです。
瞑想の姿勢の種類はなんでもいいのか?目的と効果などを解説!
心も身体も安定することで能力を発揮しやすくなるので、多くの瞑想では姿勢や呼吸を整え心身を安定した状態に近づけていきます。頭から骨盤までバランスを整えて、呼吸をゆったりとさせていきます。 pic.twitter.com/Sqg4dYTf08
— 相模 愚行| 印瞑想 忍術 (@IN_Guko) March 18, 2025
「瞑想はあぐらで座るもの」というイメージを持っている方は多いかもしれません。
ですが、実際は姿勢に正解はなく、目的に合っていればどんなスタイルでも構わないのです。無理なく心が落ち着けることが最も大切なポイントになります。
ここでは、基本的な座法の意味や、椅子や横になる姿勢の効果など、瞑想の姿勢とその目的を詳しく解説していきます。
瞑想の基本的な座法と姿勢の目的
| 姿勢の種類 | 特徴・メリット | 注意点・デメリット | 適したシーン |
|---|---|---|---|
| あぐら(基本座法) | 背筋を伸ばしやすく呼吸が深くなる | 柔軟性がないと膝や腰に負担がかかることも | 朝の集中瞑想、短〜中時間の瞑想 |
| 椅子に座る | 身体への負担が少なく継続しやすい | 背もたれに寄りかかると猫背になりやすい | オフィス、自宅、腰痛時 |
| 寝たまま行う | 全身の緊張がなく深くリラックスできる | 寝落ちしやすく意識が飛ぶ可能性がある | 就寝前、疲労時、ヨガニードラ |
| 横になる | 深い呼吸がしやすく体の負担も軽い | 快適すぎて瞑想というより休息になることも | 起床直後、体調不良時、昼の休憩時 |
| 正座 | 背筋を伸ばしやすく日本人には馴染みがある | 長時間だと足が痺れやすい | 短時間の瞑想、集中重視のとき |
瞑想というと、静かに座って目を閉じ、深く呼吸をするイメージを思い浮かべる方が多いかもしれません。

その中でも「あぐらをかいて背筋を伸ばす」という基本的な座法には、しっかりとした理由があります。ただ単に見た目のスタイルというだけではなく、瞑想の効果を高めるために必要な姿勢なのです。
瞑想の座法
| 座法の名称 | 具体的な姿勢の特徴 | 向いている人・シーン | メリット | 注意点・デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 安楽座(あぐら) | 両脚を前で交差し床に座る | 初心者、柔軟性に自信がない人 | 比較的負担が少なく、安定して背筋が伸ばしやすい | 足が痺れやすい、骨盤が倒れやすい |
| 半跏趺坐(はんかふざ) | 片足を反対側の太ももの上に乗せる | 中級者、ある程度柔軟性がある人 | 安定性があり集中しやすい | 股関節が硬い人には負担がかかる可能性 |
| 結跏趺坐(けっかふざ) | 両足とも反対側の太ももの上に乗せて座る | 上級者、ヨガ経験者 | 安定性抜群で深い瞑想に入りやすい | 柔軟性がないと膝や腰に強い負担がかかる |
| 正座 | 脚を折りたたんで膝を前にして座る | 日本人に馴染みがあり楽に感じる人 | 姿勢が整いやすく集中しやすい | 足が痺れやすく長時間は不向き |
| 椅子座法 | 椅子に浅く座り、背筋を伸ばして足を床にしっかりつける | 座る姿勢が苦手な人、高齢者、腰痛持ち | 背中への負担が少なく、姿勢維持がしやすい | 猫背になりやすい、椅子の形状に左右される |
瞑想では「調身・調息・調心」と呼ばれる3つの基本があります。これは、姿勢を整える・呼吸を整える・心を整える、という順番のことで、どれもバランスよく保つことが重要です。
特に最初の「調身」は、すべての土台になります。体の姿勢が崩れてしまうと、呼吸が浅くなり、心も落ち着きにくくなってしまうのです。
例えば、床に座る際に背筋をスッと伸ばすと、自然と胸が開き、呼吸が深くなります。また、骨盤を立てることで身体の重心が安定し、長時間座っても疲れにくくなるという利点もあります。この状態をキープすることで、心の内側に意識を向けやすくなり、集中力も高まるのです。
ただし、無理に正しい姿勢を保とうとする必要はありません。姿勢にばかり気を取られてしまっては、本来の目的である「心を整える」ことから遠ざかってしまいます。
もし足が痛ければクッションを使ったり、背中が辛ければ壁を使っても構いません。大切なのは、どんな姿勢であっても心が穏やかでいられることです。
このように、基本的な座法はあくまで“土台”として大切にしつつ、自分の体調や環境に合った姿勢で行うことが、瞑想を長く続けるうえでとても大切だと思います。


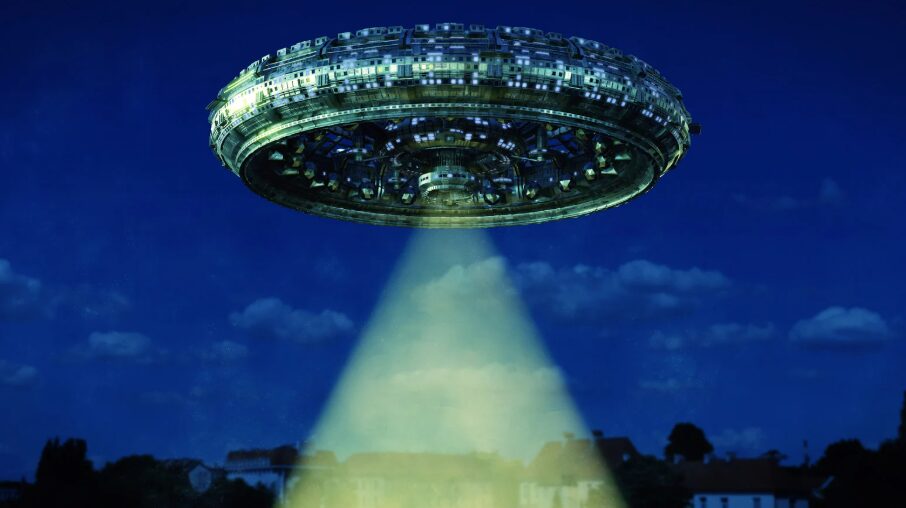

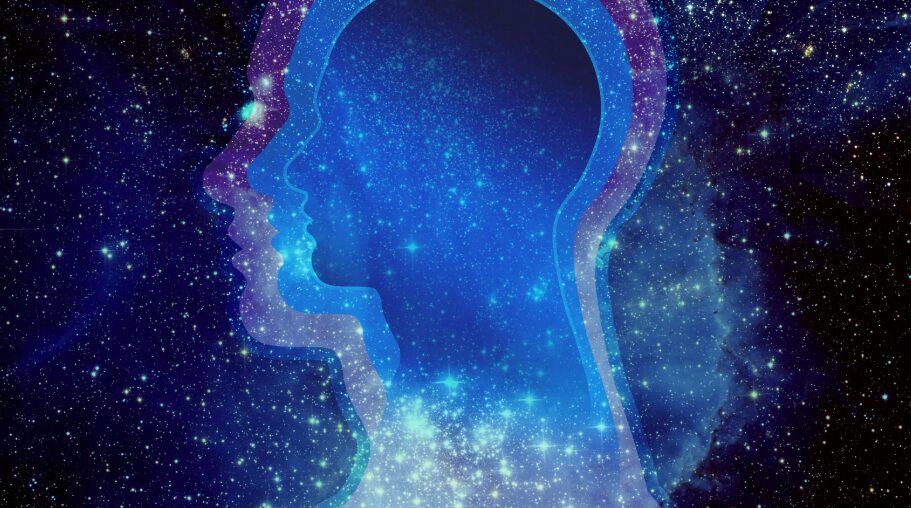

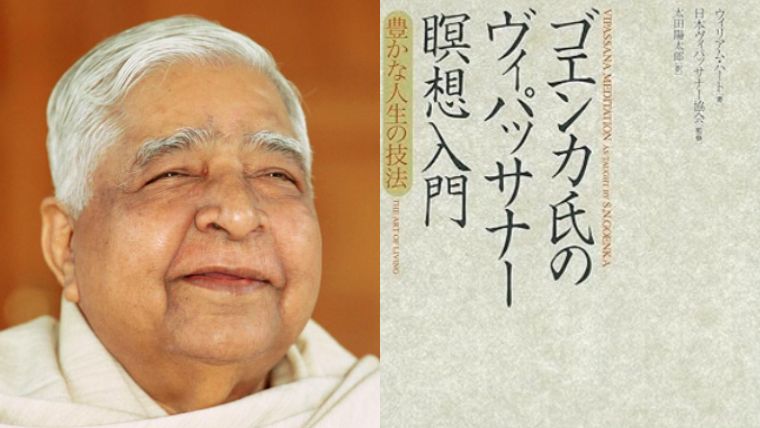

椅子に座るだけでも効果はある?

「瞑想は床に座ってあぐらで行うもの」そんな先入観を持っている人も多いかもしれませんが、実際には椅子に座って行う瞑想でも十分な効果が期待できます。
むしろ、正しい姿勢を保てるのであれば、椅子のほうが体への負担が少なく、長く集中しやすいというメリットもあるのです。
椅子で瞑想する際に気をつけたいのは、背もたれに完全にもたれかからずに、背筋を軽く伸ばすことです。お尻を椅子の前の方に置き、両足は腰幅に開いて床につけるのが理想です。こうすることで骨盤が立ち、自然と背骨がまっすぐになります。
無理に胸を張ったりする必要はありませんが、腰が丸まった状態では呼吸が浅くなりやすいため注意が必要です。

実際、オフィスでの短い休憩時間や、自宅でリラックスしているときに、椅子に座ったまま目を閉じて呼吸に集中するだけでも、気分がスッと軽くなる感覚を得られることがあります。これは副交感神経が働いて、リラックスモードに入るためだと考えられています。
一方で、柔らかすぎる椅子や背もたれが深すぎる椅子だと、体が沈み込んでしまい、猫背になってしまうこともあります。こうした場合は、背もたれにクッションを置いたり、足元に踏み台を置くなど、姿勢を保ちやすくする工夫が必要です。
このように、椅子に座っていても意識の持ち方次第で、しっかりとした瞑想状態に入ることができます。自分にとって無理のない方法で取り組むことが、継続への鍵になると思いますよ。
寝たまま行う瞑想のやり方と注意点

疲れているときや就寝前など、体をできるだけ楽にして瞑想したいと思うこともありますよね。そんなときにおすすめなのが、寝たままで行える瞑想です。リラックスしながら自分と向き合えるため、忙しい現代人には特にぴったりの方法だと言えるでしょう。
やり方はとても簡単です。まず、仰向けに寝転び、手は体の横に軽く置きます。足は自然に肩幅ほどに開き、全身の力を抜いていきます。
このときのコツは、「全身が重力に沈み込むような感覚」を意識することです。呼吸は鼻から静かに吸って、ゆっくり吐き出します。その動きに集中することで、自然と心も落ち着いてきます。
寝たままの瞑想は「ヨガニードラ」や「シャバアーサナ瞑想」などでもよく使われる方法で、深いリラクゼーションをもたらすとされています。実際、体の各部位に意識を向けながら順番に力を抜いていくと、不思議と心が軽くなり、疲れも抜けていくように感じられるでしょう。

ただし、寝たままの瞑想には注意点もあります。あまりにリラックスしすぎて、そのまま眠ってしまうことがあるのです。
もちろん眠ってしまうこと自体が悪いわけではありませんが、「瞑想」としての時間を確保したい場合には、時間を決めて行うのが良いかもしれません。また、就寝前の習慣として取り入れると、自然と入眠もしやすくなるのでおすすめです。
このように、寝ながら行う瞑想は無理なく続けやすく、心と体の疲れをやさしく癒してくれます。何より、「がんばらない」瞑想として気軽に試せるのが魅力だと思いますね。
横になって行う瞑想のメリット

体を横にした状態で行う瞑想には、心身を穏やかに整えるためのさまざまなメリットがあります。一般的な座り姿勢に比べて筋肉の緊張がほとんどなく、深い呼吸もしやすいことから、リラックス効果が非常に高いのが特徴です。
横になった瞑想では、体を片側に向けて横になる「側臥位」と呼ばれる姿勢や、仰向けになって行うスタイルがあります。
どちらの場合でも重要なのは、体を安定させて、安心して呼吸に意識を向けられる環境をつくることです。床の硬さが気になる場合は、マットや毛布を敷くと快適になります。
この体勢の最大の魅力は、やはり「緊張がほとんどない」という点です。体がリラックスしていると、脳の活動も穏やかになり、自律神経のバランスが整っていきます。
横になったまま、ゆっくりとした呼吸に意識を向けるだけで、まるで深い眠りに入る前のような心地よさを感じられることもあります。

一方で、あまりにも快適すぎるため、つい寝落ちしてしまうという声も多いです。そのため、日中に行う場合は短時間にとどめるか、目覚ましをセットしておくと良いでしょう。
また、起き抜けのタイミングで行えば、体をやさしく目覚めさせる習慣としても活用できます。
このように、横になって行う瞑想は、身体的な負担が最小限で、精神的にも深い癒しが得られる方法です。特に疲れがたまっている日や、座る姿勢がつらいときには、一番やさしい選択になるのではないでしょうか。
瞑想と睡眠との違いと境界線

瞑想と睡眠は、どちらも心と体を休めるための大切な時間ですが、両者にははっきりとした違いがあります。
とくに「寝落ちしてしまうと、それは瞑想ではなくなるのでは?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
瞑想は、意識を保ったまま呼吸や感覚に集中する“覚醒した状態のリラックス”です。つまり、意識があることが前提になります。
一方、睡眠は意識が完全にシャットダウンされ、体の回復を優先する無意識の状態です。この点が、両者の大きな違いだと言えるでしょう。
とはいえ、寝る直前の瞑想には「睡眠の質を高める」という効果があります。
就寝前に数分でも呼吸に意識を向けるだけで、脳が静まり、自然な眠気が訪れることがあります。とくに不眠気味の人や、寝つきの悪い人にとっては、瞑想が睡眠への橋渡しになることも多いのです。

ただし、眠ることを目的に瞑想をしてしまうと、「意識して内面を観察する」という本来の瞑想の目的とは少しズレてしまうかもしれません。
そのため、瞑想を行う目的が「心を整えること」なのか、「眠りにつくこと」なのかを明確にしておくとよいでしょう。
このように、瞑想と睡眠は似ているようで別物ですが、どちらも大切な時間です。使い分けを意識すれば、日々の生活の質を大きく高めることができると思います。
姿勢がツラいときの具体的対処法

「瞑想したいけど、姿勢を保つのがつらい…」そんな経験をしたことのある方も少なくないと思います。とくに初心者の方は、あぐらや正座の姿勢で体が痛くなってしまい、途中で集中力が切れてしまうこともありますよね。
このようなときに有効なのが、姿勢をサポートする工夫を取り入れることです。まずおすすめなのは、クッションや座布団を使ってお尻の位置を少し高くすることです。これだけでも骨盤が立ちやすくなり、背筋が伸びやすくなります。
太ももと床の間に空間がある人は、膝の下に丸めたタオルを入れるとより快適に座れます。
また、椅子を使うのも有効です。椅子に座るときは、浅く腰掛けて足裏を床にしっかりつけるのがポイントです。背もたれにはもたれかからず、背筋は軽く伸ばしておきましょう。こうすることで、座っているだけでも十分に瞑想状態へ入っていくことができます。
それでも姿勢がきつい場合は、思い切って仰向けや横になった姿勢で行うのも一つの方法です。無理に正しい姿勢を取ろうとするよりも、自分がリラックスできる状態であることのほうが、瞑想の質は高まります。
このように、姿勢のつらさを我慢するのではなく、自分に合った環境を整えることで、より快適に、そして継続しやすい瞑想習慣がつくれると思いますよ。
自分に合う瞑想の姿勢の種類!瞑想する時間や手足の組み方は?
座禅を組んで瞑想をする時にやる足の組み方には
— 高見譲二/未経験エンジニア見習い (@Takamimetal) May 13, 2020
結跏趺坐(けっかふざ)
半跏趺坐(はんかふざ)
のふたつがあります
慣れると長時間座っていられるらしいですが、僕は足が太いのでまず痩せることからです
半跏趺坐は片足やったらもう片方の足をやるとバランスが取れるのでベストです。 pic.twitter.com/SGk5GKZY3r
快適に瞑想を続けるには、自分の体に合った姿勢を見つけることが大切です。朝と夜、また短時間と長時間で適した姿勢が異なることもあります。
あぐらや正座に限らず、椅子を使う・寝たまま行うといった選択肢も有効です。さらに手や足の組み方によって、意識の向き方にも違いが出てきます。
ここでは、時間帯や体の状態に合わせた姿勢の選び方を紹介します。
瞑想の時間によって変えるべき姿勢

瞑想の時間帯や長さによって、最適な姿勢も変えていくとより効果的に取り組むことができます。「朝はシャキッと目覚めたい」「夜はリラックスして眠りにつきたい」など、目的によって使い分けると良いでしょう。
例えば、朝の瞑想は短時間でもOKですが、座った姿勢のほうが集中しやすく、眠気を感じにくくなります。背筋を伸ばして深く呼吸することで、脳がしっかり目覚めてくるため、1日のスタートにもぴったりです。椅子を使って5分ほどでも、心が整いやすくなります。
一方で、夜の瞑想はリラックスを目的とすることが多いため、寝転がる姿勢でも問題ありません。とくに仰向けの状態で呼吸に集中すると、副交感神経が優位になり、自然な眠気が訪れやすくなります。10〜15分程度行うだけでも、心地よい睡眠につながります。

また、長時間の瞑想を行いたい場合には、座った姿勢に加えてクッションやブロックなどを使って姿勢をサポートするのがおすすめです。体のどこかに負担がかかると、途中で集中力が切れてしまうため、道具を活用することは非常に大切です。
このように、時間帯や目的に応じて姿勢を変えていくことで、より効果的な瞑想習慣が築けると思います。自分の生活スタイルに合ったやり方を見つけてみてくださいね。
手の組み方で意識の向きを変える
せわしない12月ですが、1日のうち、ちょっとでも、気持ちを静かにさせる時間があるといいですね。
— merci (@mercicosmos) December 14, 2021
1分でも2分でも瞑想してみる。
色んな手の組み方を試して、気持ちいい、を楽しんでみます。
相変わらず、手を描くの下手〜💦 pic.twitter.com/TLzP5ZnbUj
瞑想中の「手の位置」や「組み方」について、なんとなく膝の上に置いているだけ…という方も多いかもしれません。しかし、実は手の位置や形には意味があり、それによって意識の向きやリラックス度合いが変わることがあります。
瞑想ではよく見られるのが「ムドラー」と呼ばれる手の形です。たとえば、親指と人差し指の先を軽く合わせる「ジニャーナ・ムドラー」は、集中力を高めたり、内なる平静を感じやすくする効果があるとされています。
また、両手を重ねてお腹の前で丸をつくる「法界定印(ほっかいじょういん)」は、心を静かに整える手の形として有名です。
ただし、必ずしもムドラーを使わなければならないわけではありません。手のひらを上にして膝の上に乗せるだけでも、開放的な感覚になりやすく、エネルギーが外へ向かうイメージを感じやすくなります。
逆に、手のひらを下にすると、落ち着きや内向的な意識が自然と高まっていくと言われています。
一方で、手の位置にばかり気を取られすぎると、本来の「今この瞬間への集中」という目的から外れてしまうこともあります。無理に形を作ろうとせず、自分が一番自然に感じる手の位置を探っていくのがよいでしょう。
このように、手の組み方ひとつで瞑想の雰囲気が変わってくるのは面白いですね。気分や目的に応じて手の位置を変えるだけでも、新しい発見があるかもしれません。
足の組み方による安定感の違い

瞑想中の足の組み方にはいくつか種類がありますが、それぞれに特徴があり、体への負担のかかり方や安定感に違いがあります。自分の体の柔軟性や姿勢のクセを理解しながら、無理のない組み方を選ぶことが大切です。
最もよく知られているのが「あぐら(安楽座)」ですが、これは両脚を前に交差して座る方法で、初心者にも取り入れやすい姿勢です。背筋が伸ばしやすく、足首や膝への負担も比較的少ないため、日常的な瞑想にはぴったりです。
もう少し深く組むスタイルに「半跏趺坐(はんかふざ)」や「結跏趺坐(けっかふざ)」があります。これらは片足または両足を反対の太ももの上に乗せるスタイルで、安定感が非常に高く、長時間の瞑想にも適しています。
ただし、股関節の柔軟性が必要となるため、無理をすると痛みや痺れが出ることもあるので注意が必要です。
足を楽にする工夫としては、膝の下にクッションを入れたり、お尻の下に座布団を敷いて骨盤を立てる方法があります。こうすることで、背筋が自然に伸び、足への圧迫も軽減されて、長く集中しやすくなります。
また、正座が楽だという方もいます。日本人にとって馴染みのある座り方ですが、長時間座ると足が痺れてしまうこともあるため、時々足を動かしたり、下に座布団を敷くなどの対策が必要です。
このように、足の組み方には正解はなく、自分の体に合った方法を見つけることが一番です。座るときの快適さは、そのまま瞑想の質にもつながってくると思いますね。
背もたれを使うと猫背になる?

椅子に座って瞑想をするとき、「背もたれに寄りかかってもいいのか?」と悩んだことがある方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、背もたれの使い方によっては、猫背を引き起こし、瞑想の効果を下げてしまう可能性があります。
背もたれに完全にもたれてしまうと、骨盤が後ろに倒れ、背中が丸まってしまいやすくなります。この状態だと呼吸が浅くなり、内臓への圧迫も強くなるため、リラックスしにくくなってしまうのです。
集中しようとしても、体の不快感が気になって思考が散ってしまう…という悪循環に陥ることもあります。
それでも、腰痛持ちの方や長時間の瞑想をする場合には、背もたれが必要になることもあるでしょう。
その場合は、腰にクッションを挟んで骨盤が立つようにサポートしたり、背中の上部ではなく下部を支える形で背もたれを使うと、自然な姿勢をキープしやすくなります。
また、椅子の座面に深く座りすぎないこともポイントです。浅めに腰掛けて、背筋を軽く伸ばし、肩の力を抜くだけで、十分に集中しやすい姿勢になります。
足の裏がしっかり床につき、膝が直角になっている状態が理想です。
つまり、背もたれは使い方次第でサポートにもなれば妨げにもなるということですね。自分の体の状態と相談しながら、姿勢を微調整してみると、より快適に瞑想を行えるようになると思います。
無理のない姿勢が集中を深める理由

瞑想を行う上で「姿勢は大事」と言われますが、それは決して“正しい形”にこだわることではありません。むしろ、本当に大切なのは「無理のない姿勢」であることです。リラックスできる姿勢でいることが、結果として集中力を深めることにつながっていくのです。
人の身体は、わずかな不快感でも無意識にそれを感じ取っています。例えば、膝が痛い、背中がつらい、足が痺れる…こうした小さな身体の不調があるだけで、意識は常にその“違和感”に引っ張られてしまいます。
そのため、どれだけ「呼吸に集中しよう」と思っても、雑念が次々と浮かびやすくなってしまうのです。
一方で、自分にとって自然で快適な姿勢で座れていると、身体の感覚に意識を取られずに済みます。その結果、心の動きにじっくり向き合う余裕が生まれ、瞑想に集中しやすくなるのです。
つまり、「姿勢を整える」というのは、見た目の美しさのためではなく、集中できる“環境”をつくるための工夫なのです。

具体的には、クッションを使って骨盤を立てたり、椅子を活用して無理のない高さで座ったりする方法が効果的です。
人によっては横になったほうがリラックスできる場合もありますし、短時間なら立ったままでも構いません。
また、「正しく座らなければならない」と思い込みすぎると、それ自体がプレッシャーになってしまうこともあります。瞑想中の心の安定には、身体の快適さが深く関わっているということを、ぜひ覚えておいてください。
このように、無理のない姿勢こそが、瞑想における集中を高める大きな鍵になります。頑張らないことが、実は一番効果的だったりするのかもしれませんね。
どうしても姿勢が気になる時・瞑想ツール
瞑想は呼吸しやすい姿勢としにくい姿勢を最初に感じ取るところからやるとコツ掴みやすい。腹式呼吸なんだけど楽に大量に空気を吸えて吐き出せる姿勢がある。座禅の姿勢でやるなら座布があると位置が安定するのでオススメ。 pic.twitter.com/yod30DjuFY
— ViVi (@ViVi_POKER) April 3, 2025
どうしても姿勢が定まらない・座るのがしんどいという時はツールも有効です。
【まとめ】瞑想の姿勢の種類はなんでもいい?最適な方法をわかりやすく紹介!
今回のまとめです。
- 瞑想では姿勢・呼吸・心を整える「調身・調息・調心」が基本である
- 座法では背筋を伸ばし骨盤を立てることで呼吸が深くなる
- 椅子に座っても背もたれを使いすぎなければ効果的に瞑想できる
- 寝たまま行う瞑想は深いリラクゼーションに適している
- 横になる姿勢は体への負担が少なく初心者にも向いている
- 瞑想と睡眠は意識の有無が大きな違いである
- 姿勢がつらいときはクッションや椅子を活用するとよい
- 時間帯によって適した姿勢を使い分けることが効果を高める
- 手の組み方によって集中の方向性や気分が変わる
- 足の組み方は柔軟性や体格に合わせて選ぶべきである
- 背もたれを使う際は猫背にならないよう工夫が必要である
- 無理のない姿勢が瞑想の集中力と継続性を支える要因となる
瞑想は「あぐらで座るもの」という固定観念があるかもしれませんが、実は姿勢の選択肢は非常に幅広く、体に無理のないスタイルで行うことが重要です。
基本的な座法は確かに効果的ですが、椅子に座る、横になる、寝たまま行うなど、自分に合った姿勢があればそれで問題ありません。集中しやすさや快適さは人それぞれ異なり、瞑想の時間帯や目的によって最適な姿勢も変わります。
また、手や足の組み方ひとつでも意識の向き方が変化し、猫背を防ぐ工夫も必要です。睡眠との違いを理解しながら、無理のない姿勢で行うことで瞑想の効果をより深く得られるでしょう。
自分にとって一番心地よく続けやすい方法を見つけることが、長く習慣化するコツだと思いますね。